
20代後半から30代前半にかけて、いわゆる「働き盛り」と呼ばれる年齢の時期、ついつい無理をしてがんばりすぎた、という経験がある人も少なくないだろう。
だんだん仕事を覚えて楽しくなってきたからかもしれないし、成長実感を持てているからかもしれない。でも、結局のところそれは、この身が健康無事で、「今日も明日も自分が働き続けられる」という、暗黙の前提に立っているだけなのかもしれない。
じゃあ、その前提が突然崩れたとしたら、自分はいったいどうするのだろう?
病気になり、この身体が自由に動かなくなったとき、家族や恋人、職場には何をどう話すのか。
描いていた「未来」を諦めることになったとき、それでも希望を語れるだろうか。絶望しないでいられるだろうか。
そんな宛てどころのない僕の問いに、応えてくれる人がいた。
凛とした佇まいと、やわらかな笑顔。ある日の東京での出会い
彼の名は、武藤将胤(むとうまさたね)さん。

身体の運動機能が徐々に失われていく難病、ALS(筋萎縮性側策硬化症)の当事者であり、コミュニケーションクリエイターだ。
ある日の午後、武藤さんと待ち合わせをし、街を一緒に歩いた。

ALSの症状が進み、武藤さんは自分の足を使って歩くことが難しくなってきている。
だけど、パーソナルモビリティ「WHILL」を手足のように操り、自身でプロデュースしたボーダレスウェア「01(ゼロワン)」のパンツとジャケットを身にまとったその姿は、とても凛としていてスタイリッシュだ。

お互いの共通の知人や仕事での共通点のことを話しながら移動する道中。初対面の相手にもフランクに語りかけてくれる武藤さんの醸す雰囲気は、とてもやわらかくて居心地がよく、すぐに彼の人柄に魅力を感じている自分がいた。
テクノロジーとコミュニケーションでALS当事者の可能性を拡げる「WITH ALS」
武藤さんの身体に発症したALSは、まだ治療法が確立されていない進行性の難病だ。世界で約35万人、日本には約1万人の患者がいると言われている。
体を動かす運動ニューロン(神経系)が変性し、徐々に壊れてしまう疾患で、手足を動かすことが難しくなり、次第に食事や会話、コミュニケーションも困難になっていく。身体症状の進行に対して、意識や五感、知能の働きは正常のまま。最終的には呼吸障害を起こすため、延命のための人工呼吸器の装着が必要となる。
40代〜60代での発症が比較的多いALSにおいては珍しく、武藤さんは若年性で発症したALS当事者だ。
大手広告会社に勤務し、20代前半から広告プランナーとしてのキャリアを積んできた。さまざまなプロジェクトを手がけ、仕事もますます充実する日々。恋人との結婚も考えていた矢先のALS宣告。27歳の秋のことだった。
そんな武藤さんは、ALS診断以後も、日に日に自由がきかなくなる身体とともに、たくさんの人たちとつながりながら発信を続けている。
ALS当事者としての体験と自らのクリエイティビティを通して、ALSやその他難病患者、その家族、非患者のQOL(Quality of Life)の向上に貢献するコンテンツ開発・支援活動を実施する団体「WITH ALS」を2016年に立ち上げた。
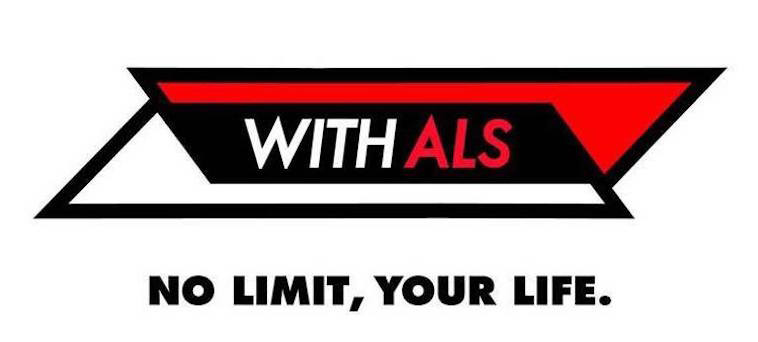
介護保険が使えない若年ALS患者向け、パーソナルモビリティ「WHILL」のカーシェアリングプロジェクト
病気、育児、介護、物理的距離、様々な制限を抱える方の「働く」意志をテクノロジーの力で支援する、「働くTECH LAB」ロボットテレワークプロジェクト
手足の自由が限られている人でも簡単に、スタイリッシュに着こなすことができるボーダーレスウェアブランド「01」
ALS患者が発症後も正常に機能を保つことができる眼球の動きだけで、メガネ型ウェアラブルデバイスJINS MEMEを使用して、DJとVJを同時にプレイするシステムやスマホやIoTデバイスをつなぐアプリ「JINS MEME BRIDGE」を共同開発する「FOLLOW YOUR VISION」プロジェクト
などなど…ALS当事者やその周囲の人達の可能性を拡げるプロジェクトを次々と手がけている。
いったい、どんな人なんだろう。彼のエネルギーやクリエイティビティの源泉はどこにあるんだろう。若くしてALS当事者となって、いま彼は何を思うんだろう。
原体験、キャリア、「コミュニケーション」にかける思い、ALS発症前後から今に至るまでの日々…武藤将胤という人の生き方を、その物語を知りたいと思った。

アイデアと行動で、きっと世界は変えていけるーアメリカの映画から学んだ、幼少期の原体験

聞き手・鈴木悠平(以下、鈴木):今日はよろしくお願いします。
武藤将胤さん(以下、武藤):よろしくお願いします。
鈴木:今日お会いするまでに、動画などで武藤さんの言葉や手がけてきたプロジェクトをたくさん拝見してきました。本当に、見ているだけでワクワクするようなお仕事ばかりで…同じくメディアやコミュニケーションに携わっている人間として、悔しさすら覚えました(笑)
武藤:ありがとうございます(笑)

鈴木:これは武藤さんが名乗っている「コミュニケーションクリエイター」という肩書きにも関わってくると思うのですが、全体を通して印象的だったのは、単なる発信に留まらずに、それを見た人の”体験”までしっかり意識してデザインされているんだなということでした。
武藤:もともと「コミュニケーション」という領域は、新卒で博報堂という広告会社に入ってから仕事上でも1番大事にしてきたテーマだったんです。昔みたいに、CMを作ればみなさんに届く、っていう時代ではなくなってきたなか、動画や音楽や洋服など…手段は本当に幅広く捉えて、いかにみなさんに感じて、体験までしてもらえるかというのを意識して発信するようにしていますね。
鈴木:確かに、フットサルのイベントや、JINS MEMEとコラボしてのDJ・VJパフォーマンスなど、武藤さんと同じ場にいる人たちがそこでの体験を楽しみながらALSについても知っていけるような仕掛けになっているなと感じました。

フットサル大会「Full Heart vol.2」とのコラボレーションイベント。武藤さん自身の経験を語ると共に、身体の筋肉が動かせなくなる状態の疑似体験「GORON for ALS」という企画を実施。
武藤:WITH ALSを立ち上げるときに念頭にあったのは、2014年の夏に行われた「アイス・バケツ・チャレンジ」というキャンペーンでした。
鈴木:氷水をかぶるかALS協会に寄付するかという選択肢で、指名性の動画リレーを行うというキャンペーンでしたね。世界中の著名人が参加して、賛否両論含めものすごく話題になりました。
武藤:実際にあのキャンペーンで寄付はかなりの額が集まりましたし、ALSという言葉自体は社会の中である程度知られるようになったと思います。
ただ、キーワードとしての認知はされたけども、ALSという病気が実際にどういう病気なのかという理解まではなかなか至らなかったというのが、実体験として感じた部分だったんですね。
ALSはまだまだ治療方法が確立されていない病気です。ALSという病気を抱えて生きる当事者は、症状が悪化していく中でだんだんと生活が苦しくなっていきます。ALSの人たちに対して周囲からの具体的なサポートが広がっていくためには、やはり言葉の認知だけでは足りなくて、症状や生活面への理解にまでつながるような、深い体験ができるコミュニケーションというのが必要だと思っています。
鈴木:ALSを取り巻くコミュニケーション上の課題はおっしゃる通りなのですが、そもそも武藤さんが「コミュニケーション」というものに強い思い入れを持つようになったのは、どういった原体験からなのでしょうか。
武藤:きっとそのルーツは、僕が生まれ育ったアメリカのL.A.(ロサンゼルス)にあると思います。
鈴木:L.A.に。
武藤:僕の幼少期は、映画に育てられたと言っても過言ではないくらい、L.A.で本当にたくさんの映画を観て育ちました。例えば「スター・ウォーズ」や「バック・トゥー・ザ・フューチャー」を観てテクノロジーの可能性に心打たれたり、音楽、ファッション、テクノロジーと、映画の中の世界で観るもの全てに刺激を受けて育ちました。
映画を観終わるたびに、その映画のパート2、パート3のストーリーを勝手に自分で考えるような少年だったんですよ。家で人形や組み立てブロックを使って、プシュプシュ言いながら新しいストーリーを妄想していたので、両親から「プシュプシュ男」って言われていました(笑)
自分自身も映画を観て刺激を受けた本人ですから、映画のストーリーを考えるときには「どうやったら観た人が喜んでくれるだろう」とか「どうやったらみんなが笑顔になってくれるだろう」といったことをいつも自然と考えていました。
鈴木:小さい頃からその発想を持っていたなんて、すごいですね。なんというか、映画による“天然の英才教育”みたいな…
武藤:そうですね(笑) 自分にとっての「コミュニケーション」の一番のルーツにはアメリカでの映画体験があると思います。
鈴木:特に大きな影響を受けた映画ってありますか?
武藤:めちゃくちゃあるんですよね、そういう映画…でも、幼少期に観たなかで特に印象が強かったものと言えば、「フリー・ウィリー」っていうシャチと少年の物語ですかね。
母親に捨てられて孤児院に入った少年ジェシーが、ある日さびれた水族館で泳ぐ1匹のシャチ、ウィリーと出会うんです。ウィリーも実は母親から引き離されて水族館に連れてこられた境遇なんですが、ジェシーとウィリーはどんどん心の距離を縮めていって、最後にはシャチを海に逃してあげるというストーリーなんです。たとえ小さな子どもであっても、自分の行動で現状を変えていけるんだっていうことに、すごく勇気をもらった映画です。

鈴木:小さな少年でも、自分で現状を変えていける…
武藤:僕の拡大解釈かもしれないんですけどね。「自分自身の手で、社会や世の中は変えていけるんだ」っていうメッセージをすごく感じたんです。
ジェシー少年が手を挙げた合図に応えて、ウィリーが壁を飛び越えて海に飛び越えていくシーンがすごく象徴的で、今でも大好きなビジュアルです。
鈴木:いま、話を聞いているだけでも情景が浮かんできました。
武藤:「フリー・ウィリー」は映像としても海がものすごく美しかったり、音楽もマイケル・ジャクソンの曲が主題歌だったりと、その世界観全体が素晴らしくて。「コミュニケーションには本当にいろんな手段があるんだな」ということを学ばせてもらった映画でもあります。
そういったアメリカでの映画から学んだことが、「コミュニケーションには人を突き動かす、世の中を明るくする力がある」という信念につながっています。次第に、自分自身でもそんなコミュニケーションを作りたいという思いが強くなり、大学生の頃には、「社会を明るくするアイデアを形に。」というのが、僕のビジョンになっていました。
大学時代では自分で学生団体を立ち上げて、ファッションショーを一から作り上げたり、渋谷の街のお店の方々に協力していただいて一緒にイベントを作ったり、学生のアイデアでCMを制作する「学生CMコンテスト」という企画を仕掛けたり…いろんなことをやりました。
ミスコンの初開催やフリーペーパー制作などもやっていましたが、従来の限られた手法で留まることなく、「本当はもっと、コミュニケーションには幅があるんじゃないか」「もっといろんな方法で人を動かしていけるんじゃないか」という意識が昔から強かったですね。
鈴木:なるほど。幅広いアイデアと方法で、世の中を明るくするコミュニケーションを作っていく…幼少期からWITH ALSに至るまで、ずっと通底する思いがあったんですね。
「どうして自分なんだろう」20代後半でのALS発症。突きつけられた現実の前に、自分のミッションを再認識した
鈴木:ここからは、武藤さんがALSを発症してから「WITH ALS」の立ち上げに至るまでのお話をお聞きできればと思います。
僕が武藤さんのことを知った時、まず思ったのは「広告会社の20代後半って、キャリア的にはものすごく働き盛りの時期での発症だったんだな」ということでした。
武藤:そうですね。広告会社っていうのは本当に自分の“天職”だなって思えるぐらいにチャレンジングな環境で、仕事もますます充実していた時期でした。

鈴木:ですよね。僕も少し歳下ですが武藤さんとほぼ同じ世代で、メディアやコミュニケーションに関わる仕事をやっているので、今まさに実感しています。
まったくの新人だった頃とは違ってスキルもついてきたし、いろんな人を巻き込みながらチームで仕事ができるようになっていく。働けば働くほど、自分の行動でプロジェクトを前に進めていけるし、何がしか世の中にインパクトを与えられたかなっていう、成功体験も積めてくる頃だと思うのですけれど。
武藤:ええ。
鈴木:それなのに、そのタイミングでALSになって。自分も周囲の同僚も、「毎日、出来ることをどんどん増やしていく」というベクトルの中で働いていたのに、自分だけが「今日出来ていたことが、明日出来なくなるかもしれない」っていう真逆のベクトルに置かれてしまうことって、いったいどんな気持ちだったんだろうと。

武藤:おっしゃる通りで、正直「なんでこのタイミングで自分なんだろう」って思いましたね。
発症は2013年の10月頃、異変は左手の握力の低下から始まりました。最初は単なる疲れだろうと思っていたけれど、休んでも症状が治まらなくて、やっぱりおかしいなと思って通院したんです。だけど、医師から返ってきたのは「原因はわかりません」という答え。最初に通っていた都内の病院にはALSへの専門的知見を持つ医師が少なくて、1年ぐらい通院して、1ヶ月入院しての集中検査も行ったんですが、そこではALSとは判明しなかったんですね。
それでも、身体はどんどん悪くなっていって。おかしいなと思ってインターネットで調べてみたら、ALSの症状に酷似していることに気付いたんです。
鈴木:そうだったんですね。
武藤:正直、最初は自分も信じたくはなかったんですけど、やっぱりはっきりさせた方が良いだろうと思って。仙台の東北大学に専門の教授がいるということを知ったので、セカンドオピニオンをもらおうと訪ねていきました。2014年の10月27日のことです。そこで、ALSの宣告を受けました。
鈴木:発症から1年経って、そこで初めて…。
武藤:仙台から東京に戻る新幹線での2時間、「なんで自分なんだろう」「どうして、このタイミング」なんだろうっていう問いを、何度も何度も反芻していました。本当に、めちゃくちゃ悩んで…丸一日電車に乗っているような感覚で。

鈴木:その2時間が。
武藤:本当に長かったですね。でも、悩んで、悩んで、考えていくうちに原点回帰させられたというか…ALSになったとしても、いやALSになった今だからこそ「社会を明るくするアイデアを形にしていくコミュニケーションをつくる」のが、自分に与えられたミッションなんじゃないかという思いが生まれてきたんです。
ALS患者の余命は3〜5年と言われていて、自分がその当事者になった。本当に、残された時間はわずかかもしれない。じゃあ、「どうして自分なんだろう、なんでこのタイミングなんだろう」。もしかして、これまでの経験を活かして「ALS患者の世界を明るくする」ということを、今まさに自分が実践するべきときなんじゃないかって。
その時は、「WITH ALS」というようなネーミングも何も決まっていなかったのですが、とにかくやろう、自分がそれをやろうとだけ決めて、東京に降り立ちました。
鈴木:決めたんですね、新幹線の中で。
武藤:すぐに、当時付き合っていた妻に電話をして、「やっぱりALSだったよ」っていう報告と同時に、これからやることについて話しました。さすがに驚いていたけれど、でも同時に安心もしてくれたみたいです。僕がもう「前を向いている」ということがわかったので。
テクノロジーとコミュニケーションが拡げる、ALS当事者の可能性
鈴木:人生のミッションを再定義した武藤さんが、最初にアップしたのが、2015年1月1日の動画でしたね。
朝の公園、定点カメラで長回し。動画タイトルも「2015/01/01 vol.1」とシンプルに日付だけ。まだ「WITH ALS」という団体もない状態で、武藤さんご自身も今より知名度があったわけではなかったと思うんですけど、それだけに力が伝わってきて、思わず見入ってしまいました。
武藤:活動のスタートを切るためにも、自分がALSという病気と向き合っていくんだという決意表明が必要でした。自分の思いの丈を喋り切るという、ただただそれだけの動画だったんですけど、多くの反響がありましたね。まだ当時はALSであることを近しい友人や家族にしか伝えていなかったので、あの動画で初めて知って驚いたという知人の声も多かったですが、応援のメッセージや、同じALS当事者ですという人からのコメントもいただきました。
鈴木:「vol.1」の動画だけ、エンドロールで表示されるのが「FUCKIN’ ALS」でしたね。仮のロゴだったと思うんですけど、あぁこれが正直な気持ちなんだろうなって。
武藤:キツイ言葉ではあるので、ゆくゆくは絶対に変えないとなとは思いつつ…でも、それぐらいの思いでALSと向き合って乗り越えてやるぞという、自分にとっての覚悟の言葉でしたね。

鈴木:その後正式に立ち上げた「WITH ALS」のミッションや活動について教えていただけますか。
武藤:一番の目的は、ALSの患者さんやその他難病当事者のみなさん、そしてそのご家族や周囲の方々のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を上げていくこと。症状が進んでいくなかでも、どうやって自分らしく自分の人生を描いていけるのか、ということを考えながら、様々なプロジェクトを実施しています。
いまは、ボランティアスタッフも入れて10数名のチームなんですが、僕がもともと広告プランナー・クリエイターとしてのキャリアを歩んできたこともあって、けっこうクリエイター系のメンバーが多いですね。プロジェクトごとに、その都度外部の方も含めて最適なチームを組んで動いています。
鈴木:数々のプロジェクトをご覧になっていて思ったのは、これまでお話いただいた「コミュニケーション」に対するこだわりはもちろん、そのアプローチ方法として「テクノロジー」をかなり積極的に活用されているなと。
武藤:そうですね。テクノロジーの力をうまく発見・開発することで、今までALS患者では不可能と思われていたことが可能になったり、自分でライフスタイルを選択できるようになる可能性が十分にあると思っています。
ALSという病気は40代〜60代での発症が平均的です。いま日本におられる患者さんには60〜70代の高齢の方もとても多くて、僕のような若い患者はまだまだレアケースです。一方で、僕たち若い年代が得意で、感度が高い領域はやっぱりテクノロジーだと思うんですね。
そのテクノロジーの力を存分に引き出せば、今までALS患者の限界だと言われていたところを突破できるはず。「NO LIMIT, YOUR LIFE.」というWITH ALSのスローガン通り、ALS患者を含め、全ての人に限界はないんだっていうことを、明るいニュースとして届けていきたいんです。

鈴木:明るいニュース…まさにおっしゃる通りで、WITH ALSのプロジェクトやそのプロモーション動画は、ALS患者以外の人も含めて、見ている人の気持ちを明るくさせたり、希望を感じさせたりするようなものばかりでした。
武藤:僕は正直、“障害者用”と限定されたテクノロジーやサービスはあまり好きではないんです。僕は両方を経験しているのでなおさら思うのですが、本来、障害者と健常者という垣根なんかないはずだと思うんですね。
WITH ALSのカーシェアレンタルサービスに「WHILL」を使用したのにもそうした思いがありました。“車椅子”というと、どうしても障害者用の乗り物というイメージがついてしまっていて、僕自身も前向きに「乗りたいな」と思えるものがあまりなかったんです。一方でWHILLは“パーソナルモビリティ”と銘打っていて、障害がなくてもみんなが「乗りたい」と思えるようなカッコイイデザインと機能を兼ね備えていました。WHILLのようなプロダクトが増えていけば、もっと一人ひとりが前向きな気持ちで選択できるようになると思います。

介護保険が適用されない40歳未満のALS患者に向けた、パーソナルモビリティ「WHILL」のカーシェアレンタルサービス。
武藤:もう一つ例を挙げると、メガネ会社のJINSさんとコラボした「FOLLOW YOUR VISION」プロジェクトでも発見がありました。それは、障害者にとって、テクノロジーは決して意思伝達のためだけの道具ではないということ。
ALSの患者さんって、高齢の方でも視線入力装置で介助者とコミュニケーションを取っている方ってけっこう多いんですね。なかなかハイテクなおじいちゃんおばあちゃん集団だなと(笑)
鈴木:そうなんですね。
武藤:でもそこで同時に思ったのは、本当はみんな、そうした最低限の意思伝達だけじゃなくて、もっと健常者と同じく「表現の自由」を楽しめたっていいんじゃないかということなんです。
目しか動かせないなら、じゃあもっと目だけで出来ることを増やしていくものが作れないか、と思って、自分がもともと音楽・映像が好きでDJをやっていたこともあったので、「目だけでDJとVJをやってしまおう」というアイデアで始めたのがJINSさんとのプロジェクトでした。

メガネ型ウェアラブルデバイス「JINS MEME」を活用し、DJとVJを眼の動きだけで同時にプレイするシステムを開発した「FOllow Your Vision」プロジェクト。
武藤:視線やまばたきだけでDJ・VJをできるようにするという、かなり極端なアプリを開発したわけですが、そこでベースとなった技術を活用して、まばたきだけで照明のON/OFF操作をしたり、スマホカメラのシャッターを切ったり、テレビやエアコンのスイッチをつけたりと…日常生活での行動を拡げられるような応用技術の開発にもつながってきています。
鈴木:それはすごいですね。武藤さんの問題意識やアイデアが、どんどんALSの人たちの生活を変えるプロダクトへとつながっていて、まさに「社会を明るくするアイデアを形に。」していっているように思います。
武藤:そうですね。大きなビジョンを掲げて行動し続けていると、近いビジョンの人には必ず巡り合えるということを実感しています。広告会社時代には出会わなかったような人たちとの出会いや、一緒にお仕事をする機会がすごく増えましたね。
悩みに悩んだ、恋人へのプロポーズーそれでもあなたと、共に歩みたい
鈴木:これまで、武藤さんの生い立ちや原体験、ALSを発症してから今に至るまでを聞いてきましたが、そんな武藤さんの挑戦を最も近くで見てきた存在、パートナーの木綿子さんとの関係についてお聞きして良いですか。付き合いだしたのは、ALS発症前、そしてプロポーズはALS確定後と、もっとも大きな変化があった時期をともに過ごしていたと思うのですが…。
武藤:そうですね、僕にとっても彼女にとっても、プロポーズと結婚というのは、一番大きなターニングポイントだったと思います。
発症をしてALSと確定するまでの時期は、ちょうど結婚について二人で相談し合っていたタイミングに重なるんです。仙台でALSの確定宣告を受けたのが、もともと自分がプロポーズをしようと思っていた予定日の2ヶ月前で、「このまま彼女にプロポーズをしていいのか」というのは、当時一番悩んだことでした。
ALSは進行性の病気なので、一緒に暮らしていく以上、彼女にも介護をしてもらわなければいけません。その負担をかけてまで結婚生活を送っていくことは、もしかしたらかえって彼女を不幸にしてしまうかもしれない。そんな思いもありました。
彼女のご両親は、子どもの頃から彼女のやりたいこと全部に賛成し、応援してくれるようなご両親だったんです。だけど、僕との結婚については初めて反対の意思を示されたということを事前に聞いて…それで余計に悩みました。

鈴木:ALSになる前に思い描いていた結婚生活とは、違った日々が待っている。それはお互い、悩みますよね…。
武藤:それでも、ALSになる前も後も、彼女と一緒にいたいという思いは変わりませんでした。だからちゃんと思いだけは伝えよう、断られてもしょうがないから、ちゃんとプロポーズだけはしようって決めたんです。
普通、プロポーズするときって大抵は「OKしてもらえる」ことへの期待は持てている状態だと思うんですけど、僕の場合は「せいぜい五分五分だろう」って気持ちで。
鈴木:五分五分かぁ…。

武藤:マジで五分五分でした(笑)まったく自信はなかったですね。
プロポーズは、すごくベタなんですけど…彼女の誕生日に、彼女が大好きなディズニーランドのシンデレラ城の前で行いました。
「必ず、全部の壁を一緒に乗り越えて、あなたを幸せにします」
彼女は僕の言葉を聞いた瞬間、うわっと泣いて。
彼女は僕の性格もよく分かっているので、「もしかしたら、私のことを気遣って、プロポーズしてくれないんじゃないか」と思っていたみたいです。だから本当に喜んでくれていました。
鈴木:そうだったんですね…お互いに「もしかしたら」と悩んだ末の婚約、本当に嬉しかったと思います。
武藤:当時約束した通り、今でも一緒に暮らしていてたくさんの大きな壁にぶつかります。だけど常に、「その壁をどうやったら乗り越えられるのか」っていうことを考えるようにしていますね。それが彼女との約束なので。
鈴木:きっと暮らしていくなかでたくさんの困りごとがあると思うのですが、お二人でどのように話し合って乗り越えていますか。
武藤:何より大事なのは、僕のALSの進行を予想しながら、常に早め早めに彼女と共有して対策を講じていくこと。今までは、ライフもキャリアも、「こうしていこう」と自分たちの意思で描いて積み上げていけるようなものでした。ALSになってからは、症状の進行に合わせて、どんどんライフスタイルの方を柔軟に変えていかなくてはなりません。
正直僕も、身の回りの介護は彼女に見てもらうのが一番安心です。でも彼女にも、彼女の人生ややりたいことがありますよね。どんどん重くなっていく症状に対して、僕のケアを100%彼女に頼ってしまうと、彼女の身体にもすぐ限界がきてしまいます。
だから、介護サービスの利用などは、なるべく早め早めに決めて、彼女にかかる負担を分散していくことが大事だと感じています。身体の負担でお互いパツパツになってしまうと、心の余裕も生まれにくくなってしまうので、二人で前向きに生きていくためにも、今後も柔軟に体制を変えていこうと思っています。

鈴木:これからも二人で生きていくためにも、依存先を分散させていくというのが大事になっていきますよね。このことは、WITH ALSの活動をはじめ、武藤さんの「仕事」の場面でも同じだと思うんです。働く上での、周囲の人との関わり方や仕事の進め方についても、変化はありましたか。
武藤:仕事の面でも、ものすごく変化がありましたね。「コミュニケーションをクリエイトする」という仕事をしている僕自身が、ALSの進行によって他者とのコミュニケーションがどんどん取りづらくなっていくという経験をしているので…。たとえば手が動かなくなることで、今までは企画書も映像も自分でちゃちゃっと作れていたのが、出来なくなってしまいます。自分が手を動かせない分、みんなとどうイメージを共有して、僕のかわりにどう動いてもらうのか、仕事のアウトプット過程をどんどん柔軟に変えていかないと、これまでの方法ではやり切れなくなっているんです。
大変ではあるけれど、これも前向きに捉えて、「新しい働き方を自分で開拓していくんだ」という思いで試行錯誤しています。
誰の人生にも限界なんてないー0から1を繰り返すことで、世界は広がっていくし、変えていける
鈴木:これまで武藤さんの生い立ちから今に至るまでをお聞きして、「世の中を明るくするアイデアを」という根底の思いを知ることができました。その思いがあるからこそ、ALSになってからもこれだけのエネルギーで活動できるんだ、そして未来への希望を持って歩んでいっているんだということも、すごく伝わってきました。
……だからこそ、最後にひとつ、聞いてみたいことがあって。
武藤:はい。

鈴木:ALSというのは進行性の病気だから、やっぱり、「今日出来ていたことが明日にはできなくなるかもしれない」という可能性があるわけですよね。それを知った上で生きている武藤さんは…夜眠る前、どんな気持ちでいるんですか。
武藤:それはやっぱり…不安にはなりますよ。
「明日まだ、こうやって手足は動いているんだろうか」「まだ、声は出てるのかなぁ」って、それは本当に、リアルな不安として日々感じてはいます。
正直、「約束された時間」なんてものは僕には全くないわけで。
でも、それはALSだからということでは本来なくて。みなさん誰にとっても、時間は有限なものだし、限られた選択肢のなかで人生を生きていると思うんですよ。
鈴木:ええ。

武藤:僕はALSになったことで、その事実を目の前に突きつけられたんですよね。だから時間の大切さっていうものを、強く再認識することができたんだと思います。だからこそ、この活動を通して、ALSなどのハンディキャップを抱えた方以外に対しても、一瞬一瞬どう自分の人生を歩んでいくのかということを働きかけていくのも、自分の役割の一つなんだと思います。
毎日、怖さはあります。だけどそこを逃げても何にも解決しない。その怖さと向き合って、何か少しでも改善余地がないか、何か少しでも、無理って思ったことが可能に出来ないかって考えることが、今のクリエーションの原点ですね。日常の全ての発見が、僕のアウトプットにつながっているんです。
鈴木:何か一つでもできることがないか、何か少しでも新たに挑戦できることはないか。それこそ、0から1を…
武藤:そう、0から1を何度も繰り返す。それが僕が、「01」(ゼロワン)というブランド名に込めた想いなんです。どんな状況にいても、身体が自由に動かない人でも、0から1歩目を踏み出すことで、世界は広がっていくし、世界は変わっていくんだということを伝えたかった。一人ひとりが限界の壁を超えて新しい世界に踏み込んでいくことを応援したいし、僕自身も日々リハビリをしながら同じ思いでALSと戦っています。

武藤:自分のこれまでのキャリアを振り返ると、1のものを100に見せる仕事、というのもたくさんやってきたんですよ。だけど、僕が学生時代から掲げてきた「社会を明るくするアイデアを形に。」ということを本当の意味で実現するためには、やっぱり0から1を生み出す仕事をしていくしかないんだと思います。
ゼロ・ワンの繰り返しの先に、いつかALSという病気を治せる日が来るって信じているし、僕の活動を通して、みなさんの人生にとっても限界はないんだということを伝え続けたいと思っています。
いま現在も、数年前にイメージしてたもの以上のことが起きていっているという実感があります。でもそれは、もし行動がゼロだったら決して起こりえなかった出来事なんです。
「NO LIMIT, YOUR LIFE」、この信念の下で、僕はこれからも行動を続けていきます。それが何か、みなさんの行動のきっかけになってくれると、一番嬉しいですね。

誰にとっても、人生の時間は有限だ。だけど僕たちはつい、その当たり前の事実を忘れてしまう。明日も、今日と同じ日々が続くと思い込んで。
武藤さんと話していると、その“当たり前”が、本当はどれほどの切迫感を持った現実であるかということに気付かされる。
そして、誰にとっても時間は有限であるからこそ、たとえALSになっても、どんな状態からでも、0から1を生み出す挑戦を始めることができるし、その挑戦に限りはないのだということにも。
武藤さんと次にまた会うとき。ALSの症状はまた進行していて、彼の身体の自由に動かせる範囲はまた小さくなっているかもしれない。
でもきっと武藤さんは、その分また1つ新しい挑戦をしていて、彼や、彼と同じようにハンディキャップを抱える人たちの可能性を拡げているんだと思う。
じゃあ自分はどうするのか?この記事を書き終えたとき、改めて問い返されているような感覚を覚えた。
彼と同じ時代を共に生きる一人の人間として、他の誰とも違う、でも同じく一回きりの有限な人生を生きるなかで、自分がやるべきゼロワンに挑み続けたい。

関連記事:
WITH ALSが挑戦した次世代型電動車いす「WHILL」のシェアサービスに関する記事はこちら
ボーダレスウェアのファッションブランド『01』の記事はこちら
ALS患者であるサッカークラブ「FC岐阜」前社長の恩田聖敬さんのインタビューはこちら
(写真/加藤甫、協力/長島美菜)



